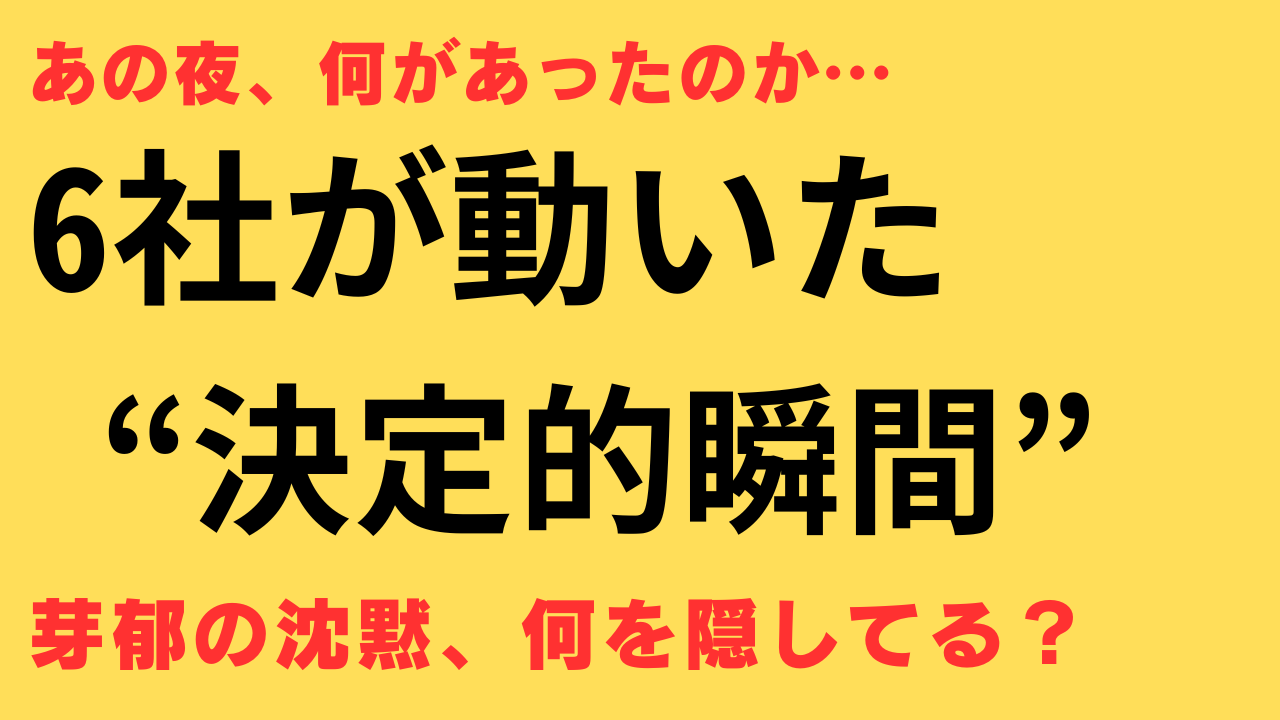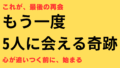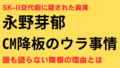「えっ…永野芽郁さんが不倫?」
そんな衝撃的な報道が飛び込んできたのは、2025年4月のこと。俳優・田中圭さんとの“関係”を『週刊文春』が報じたことで、ネット上は大騒ぎに。さらに、この報道をきっかけに、永野さんが出演していた6社のCMが相次いで削除。新作映画の取材対応も異例の「完全シャットアウト」となり、事態は深刻さを増しています。
「本当に不倫だったの?」「なぜ企業はここまで素早く動いたの?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、永野芽郁さんの不倫疑惑が波及した背景と影響、そして「貝戦略」と呼ばれる沈黙対応の狙いやリスクについて、わかりやすく紐解いていきます。今後の活動や企業との関係にどんな影響があるのか…ファンならずとも見逃せない内容です。
✅永野芽郁“不倫疑惑”報道の経緯と影響とは?
🎯文春報道が発端、田中圭との関係とは
永野芽郁さんと田中圭さんの“不倫疑惑”が初めて報じられたのは、2025年4月24日発売の『週刊文春』によるスクープです。記事では、2人が深夜に都内の高級マンションで密会していた様子や、プライベートなLINEのやり取りなどが紹介され、一気にネット上で拡散されました。
田中圭さんは既婚者であり、これまで「育メン俳優」として好感度も高かっただけに、Wショックとも言える報道内容に注目が集まりました。一方で、2人は共演歴も多く、業界内でも仲の良さが知られていたため、「親しいだけでは?」という擁護の声も一部からは上がっています。
この段階で、当事者双方とも明確な否定はせず、永野さんは後にラジオ番組で「誤解を招いたことを反省している」とコメントしましたが、交際や関係性については詳細を語らないスタンスを貫いています。この“説明しない対応”こそが、後の波紋をさらに広げることとなります。
🎯“清純派”のイメージが一転、ファンと企業の反応
永野芽郁さんといえば、透明感ある笑顔とナチュラルな演技で“清純派”女優として人気を博してきました。NHK朝ドラ『半分、青い。』や多数のCMで見せてきた誠実なイメージが、今回の不倫疑惑によって大きく揺らいでしまったのです。
報道直後から、SNSにはファンの間で動揺が広がりました。
「信じたくない」「イメージと違う」「ショックで眠れなかった」といったコメントが並ぶ一方で、「報道だけで決めつけるのは早い」「謝罪することじゃない」と擁護する声も。意見は真っ二つに分かれ、ネット上は騒然としました。
そして大きな影響を受けたのが“企業”です。清潔感や信頼性が求められるCMキャラクターとして起用していたスポンサー企業は、炎上によるブランドイメージの毀損を懸念。結果として、わずか1週間ほどの間に6社が相次いでCMを削除、事実上の“降板状態”に。
ファンの間では「企業の対応が早すぎる」「契約解除じゃないのに削除?」と疑問の声もありますが、広告業界では“速さ”が危機管理の鍵。これはまさに、芸能界の現実を映し出した一幕でもあるのです。
🎯削除されたCM6社の一覧と対応内容
不倫疑惑報道の波紋は、永野芽郁さんが出演していた企業広告に直撃しました。報道から数日以内に、合計6社が永野さんの出演するCMや広告を削除・非公開にするという異例の対応を取っています。これらの動きは、単なる報道の影響というより、企業の“リスク回避”姿勢の表れといえるでしょう。
削除を発表した企業は以下の通りです:
- サントリー(トリスハイボール)
- JCB(クレジットカード)
- サンスター(オーラルケア製品)
- アイシティ(コンタクトレンズ)
- モスバーガー(ファストフード)
- 三菱重工(企業ブランド広告)
特にサントリーは「ブランド本来の価値を伝えることが難しい」と公式に発表し、CM動画をYouTubeから削除。また、三菱重工は永野さんを起用した特設サイトを非公開にし、「影響を総合的に判断して対応中」とコメントしました。
注目すべきは、これらの企業が“契約終了”を明言していない点。つまり、出演契約は形式上まだ続いている可能性がありますが、「表には出さない」という慎重なスタンスを取っているのです。
🧾サントリー、JCBなどの削除理由
CM削除を決断した企業の中でも、特に注目を集めたのがサントリーとJCBの対応です。どちらも永野芽郁さんの起用に積極的だった企業でありながら、報道後の対応は非常に素早く、かつ明確でした。
まずサントリーは、「トリス」ブランドのCMに出演していた永野さんの動画を公式チャンネルから削除。その理由については、「現状を踏まえ、ブランドの価値を適切に伝えることが困難と判断した」と説明しています。アルコール飲料は“清潔感”や“安心感”が重視される商品カテゴリであるため、出演者のイメージが販売に直結しやすいという背景もあります。
一方、JCBは永野さんの広告ビジュアルや関連動画を静かに削除。特に公式発表は行わず、YouTubeや公式サイトから該当コンテンツを非公開にしたのみという「静かな撤退」スタイルを取りました。これは、炎上を最小限に抑える“フェードアウト戦略”の一種とも見られています。
企業にとっては、CM出演者のスキャンダルはブランド毀損に直結する重大リスク。特にSNS時代では、批判が一気に拡散されるため、対応の遅れが“企業姿勢”として問題視されかねません。だからこそ、スピーディーかつ慎重な削除判断が求められたのです。
🧾契約継続中でも非公開措置が取られる背景
一部報道によると、永野芽郁さんと削除を行った企業の間では、CM契約自体はまだ正式に終了していないケースが多いとされています。それでもCMや広告を非公開にする動きが相次いだ背景には、「契約」と「ブランド価値保護」は別問題という企業の論理があるのです。
まず、CM契約には通常、“重大なイメージ毀損が発生した場合の対応”に関する条項が含まれています。ただしこれは「違約」かどうかを判断するための基準であり、即座に契約解除には結びつかないことが一般的です。むしろ、契約継続を前提としたまま「一時的に非公開」「静観」という処置をとる方が、リスクを最小限に抑える手段として選ばれています。
また、法的な手続きや違約金の問題もあるため、企業側としては**“公にしない”ことで柔軟な選択肢を残す**意図もあると考えられます。あくまで「契約は切らないが、広告には出さない」スタンスを取ることで、批判を避けつつ今後の動向を見守る姿勢なのです。
このような非公開措置は、芸能人の不祥事が報じられた際によく使われるリスク回避戦略の一つであり、まさに現代広告における“保険”ともいえる対応といえるでしょう。
🎬主演映画でも異例の“貝戦略”、その狙いとリスク
🎯取材NG・舞台挨拶も非公開の異例対応とは
永野芽郁さんの不倫疑惑が映画業界にも波及したことで、主演映画『かくかくしかじか』の公開対応は異例の展開となりました。通常であれば、初日舞台挨拶はマスコミ取材やフォトセッションが行われ、宣伝の最大の見せ場となるはず。しかし今回、マスコミ一切NG、写真撮影も不可という“沈黙対応”が取られたのです。
この対応に、記者たちからは「異例すぎる」「あまりにも慎重すぎる」と困惑の声が上がりました。映画側の公式コメントによれば、「報道の影響を考慮し、関係者への過度な注目を避けるため」とされていますが、これが逆に“逃げ”や“非を認めたように見える”との批判も呼んでいます。
本来ならば、主演女優のメディア対応は作品の成否を分けるほどの重要なプロモーション要素です。しかし今回の“完全ノーコメント”戦略によって、作品そのものの注目度が下がる恐れや、他の共演者・制作陣への負担が高まるリスクも否めません。
まさに、「貝のように口を閉じる=貝戦略」が取られた瞬間。果たしてこの選択は、守りの姿勢として正解だったのか。それとも、後にさらなる誤解や炎上を生む火種となるのか──今後の動きが注目されています。
🎯事務所・本人コメントの内容と波紋
報道後、多くの人が注目したのが、永野芽郁さん本人と所属事務所からのコメントでした。ファンとしては「本人の口から真実を知りたい」「誤解なら早く否定してほしい」といった思いを抱えていたはずです。
しかし、永野さんが発表したのは、ラジオ番組でのわずか数分間のコメントのみ。「誤解を招くような行動があったことを反省しています」と語ったものの、田中圭さんとの関係性については一切触れず、具体的な釈明はありませんでした。
この対応に対しては、SNS上でも反応が二極化しました。
- 「あくまでプライベートの問題だから、これ以上詮索する必要はない」
- 「逃げているようにしか見えない」「説明責任を果たしていない」
といった意見がぶつかり合い、かえって混乱が拡大している印象です。
また、所属事務所も「本人が深く反省している」としつつ、詳細については「プライバシーの観点から回答を控える」とコメント。結果として、疑惑を“否定も肯定もしない”状態が続き、火消しどころか“炎上保留”という不安定な空気を生んでしまいました。
このような曖昧なスタンスは、企業や映画関係者の対応にも影響を及ぼしていると見られ、今後の方向性がますます注目される状況です。
🎯「貝戦略」とは何か?芸能界における前例も紹介
「貝戦略」とは、スキャンダルや炎上が発生した際に、一切発言をせず沈黙を貫く対応を指す俗語で、芸能界や政界でもたびたび見られる手法です。まるで“貝”のように口を閉ざすことからこの名がつきました。
この戦略には、“下手に発言して火に油を注ぐよりも、時間が風化させてくれるのを待つ”という意図があります。実際、初期対応で逆風を浴びた芸能人が、説明を控えることでやがて騒動が収束したケースも存在します。
例えば、過去に“貝戦略”が話題となった例として以下が挙げられます:
- 唐田えりかさん(東出昌大さんとの不倫騒動)
→報道後に長期間沈黙。活動再開時は露出を絞って徐々に復帰。 - 広末涼子さん(W不倫報道)
→本人はほとんど公に発言せず、事務所のみがコメント対応。結果としてCM削除・出演自粛が続いた。 - 小出恵介さん(不祥事後のメディア対応なし)
→完全沈黙の末、海外活動にシフト。
このように、“説明しないことで責任の所在を曖昧にする”ことが一種の戦略として機能する場面もありますが、同時に「説明責任の放棄」と受け取られるリスクも非常に高いです。
永野芽郁さんのケースでは、疑惑の真偽を明言しないまま、本人も事務所も慎重な対応を継続しているため、まさに「貝戦略」の典型例といえる状況です。
🧾広末涼子、唐田えりかなど過去事例との比較
永野芽郁さんの「貝戦略」対応を理解するうえで、過去の類似ケースと比較することは非常に参考になります。特に注目すべきは、清純派女優として確立されたポジションから一転、不倫報道によって活動を制限された広末涼子さんや唐田えりかさんの事例です。
◉広末涼子さんのケース(2023年)
俳優・鳥羽周作氏とのW不倫が報じられた後、本人からの詳細な説明はなく、メディア対応は事務所を通した一文のみ。
CMは一斉に削除され、テレビ番組の出演も取りやめに。完全沈黙のまま活動自粛となりましたが、復帰の兆しは見えないまま現在に至っています。
◉唐田えりかさんのケース(2020年)
東出昌大さんとの不倫が発覚後、世間のバッシングが過熱。当初は釈明なしの沈黙戦略を取ったものの、その“無言”が逆に反感を呼び、女優復帰までに約2年のブランクを余儀なくされました。
ただし、現在では一部の映画や舞台で徐々に活動を再開しています。
これらの例と比べても、永野芽郁さんの「対応を控える姿勢」は極めて近いものです。しかし、彼女がCM削除後も“契約継続中”であること、ラジオでの簡易コメントがあったことは、やや「ハイブリッド型」の貝戦略とも言えるでしょう。
ポイントは、沈黙が信頼回復の助けになるか、火種を残すだけになるか。それは対応の継続次第で、明暗が大きく分かれるのです。
🧾「説明しない」ことで生まれる逆効果の可能性
「沈黙は金」とはよく言いますが、芸能界においては必ずしもそうとは限りません。特に今の時代、SNSで誰もが意見を発信できる環境では、“説明しない”ことが新たな誤解や憶測を生む温床となる危険性があります。
今回の永野芽郁さんのケースでも、本人の言葉が「誤解を招いた行動を反省」という抽象的な一文にとどまったため、ネット上では
- 「結局、何が本当なの?」
- 「否定しないってことは認めたのと同じでは?」
- 「逃げてる印象がぬぐえない」
という声が次々に上がり、かえってイメージのダウンに拍車をかけています。
特に“清純派”としての信頼を積み重ねてきた永野さんにとって、この曖昧な対応は「期待値との落差」を生みやすく、支持層からの失望を招きかねません。
さらに、スポンサー企業や制作関係者にとっても、「今後また問題が起きたときに釈明されないのでは」という不安要素となり、起用リスクが高まります。結果として、起用見送り・キャスティング除外など、将来的な仕事にまで影響を及ぼす可能性があるのです。
つまり、“沈黙=安全”という考え方は、時に逆効果。信頼回復には、タイミングを見た誠実な説明が必要だという教訓を、過去の事例とあわせて学ぶべきかもしれません。
🏢CM削除の背景にある企業判断とリスク管理
🎯企業がタレント起用に慎重になる理由
企業がタレントを広告に起用する理由は、「好感度」や「信頼性」を商品のイメージに重ねるためです。特にテレビCMやブランドキャンペーンでは、出演者の人格や私生活も含めた“印象”がそのまま商品に直結します。
そのため、タレントにスキャンダルや炎上が発覚した場合、企業は即座に「ブランド毀損リスク」を検討しなければなりません。近年はSNSやネットニュースで情報が瞬時に広まり、企業名もタグ付けされてバッシングの対象となるケースが増えています。
「なぜこの人を起用し続けるのか?」
「この企業は社会的倫理を軽視しているのでは?」
という声が上がれば、商品の売上に影響するだけでなく、企業そのものの信用問題に発展しかねません。
こうしたリスクを未然に防ぐため、企業は契約時に「不祥事に関する条項(モラル条項)」を盛り込むことが一般的です。そして問題が起きた際は、違約や契約解除に至らなくても、「一時的な露出停止」や「削除・非公開措置」が取られるのです。
つまり、CM削除は単なる“対応”ではなく、企業が“ブランドの命を守るための防衛手段”でもあるのです。
🎯イメージ毀損とブランド価値の関係性
企業がCM削除を即断する背景には、「タレントのイメージ=商品の信頼性」という強い連動関係があります。つまり、出演者の信用が揺らげば、そのまま商品や企業への信頼まで損なわれるということです。
たとえば、清潔感が重要視される食品・日用品・金融系の広告では、出演者のスキャンダルが起きた瞬間に「その商品まで“怪しい”と見なされる」ことがあります。これは“連想イメージ”と呼ばれ、広告効果が逆転してしまう最悪のパターンです。
特に近年では、SNSを通じたユーザーの反応スピードが早く、わずか数時間で企業の公式SNSが炎上する事態も珍しくありません。
「不倫した人をイメージキャラに使うの?」
「この企業は何を考えてるの?」
といったコメントが拡散されれば、炎上リスクはCMどころか企業ブランド全体に波及します。
そのため、どれだけ長年起用していたタレントであっても、イメージ毀損が起きた瞬間に「一時撤退」や「削除判断」を下すのが今や常識。リスクマネジメントの観点からも、企業は“信用で商売している”という認識がますます強くなっています。
永野芽郁さんの場合も、スキャンダルの真偽が確定していない段階であっても、イメージが揺らいだ瞬間に「安全策」が取られたのです。
🎯不祥事発生時の広告業界の対応パターンとは?
芸能人の不祥事が発覚した際、広告業界では一定の“対応パターン”が存在します。これは企業イメージを守りつつ、法律や契約に基づいた慎重な判断が求められるため、各社が似たようなプロセスを取ることが多いのです。
主な対応パターンは以下の通りです:
- 状況の把握と社内会議(初動)
→報道直後、事実関係の確認と広報部・法務部の緊急対応が行われます。 - メディア・SNSの動向チェック(炎上リスク評価)
→世論の反応を注視し、ネットでの“燃え方”によって対応スピードが変わります。 - CM・広告の削除または一時非公開(暫定措置)
→騒動の余波を防ぐため、まずは動画やバナーを削除して様子を見るのが一般的。 - 契約内容の再検討・法的措置の判断(正式対応)
→モラル条項に該当するか、違約金の発生有無、再起用の可否などが協議されます。 - 公式見解の発表 or 発表せずにフェードアウト(最終対応)
→リスクが大きければ正式に契約終了を発表、小規模なら静かに広告展開を終了するケースも。
この流れの中で、企業は“世論の温度感”を非常に重要視します。沈静化しそうなら復活もあり得ますし、炎上が長引けば完全削除へと踏み切ります。つまり、**「判断の鍵は企業側だけでなく、世の中の反応」**なのです。
永野芽郁さんの件も、CM契約そのものは現段階で継続とされているものの、世論が落ち着くまでは「非公開対応」で様子見という典型的なパターンを踏襲していると言えるでしょう。
🧾即時削除と様子見判断の違い
芸能人の不祥事が報じられた際、企業がとる対応には大きく分けて「即時削除型」と「様子見型」の2パターンがあります。それぞれの選択には、企業のリスク許容度やブランド戦略の方針が色濃く反映されます。
■即時削除型
報道後すぐにCMや広告を削除し、表立った展開を停止するスタイルです。今回のサントリーやJCBがこのタイプで、炎上の拡大を防ぐ目的でスピード重視の対応を取っています。
メリットは「早期火消し」ができることですが、デメリットとしては「過剰反応」と批判されることや、当事者との関係が悪化するリスクがあります。
■様子見型
いったん非公開にせず、ネットやメディアの反応を数日観察したうえで、必要に応じて段階的に削除・契約解除を検討する手法です。比較的炎上リスクが低い場合や、真偽が不明なケースに選ばれます。
ただし、タイミングを誤ると「対応が遅い」として逆に批判を浴びる可能性もあるため、判断のタイミングが極めて難しい方法でもあります。
今回の永野芽郁さんのように“清純派”として長年親しまれていた場合、企業側も信頼関係を重視しすぎて様子見に走りがちですが、報道の影響が強ければ“即削除”へと切り替えるのが実情です。
つまり、企業は「本人の説明」よりも、「世間の空気」を最優先に動いているということが、この対応の差からも見て取れるのです。
🧾ネット炎上リスクとスポンサーの危機管理
現代の広告業界において、タレントのスキャンダルが引き起こす最大のリスクは、テレビや新聞ではなくSNSでの炎上です。数年前と違い、今は一人の投稿が数十万人に一気に拡散される時代。企業名や商品名がハッシュタグ付きで“吊るし上げ”られることも珍しくありません。
スポンサー企業にとっては、この「炎上の連鎖反応」が最も恐ろしいポイントです。なぜなら、火元がタレントであっても、消費者の矛先が企業に向くケースが非常に多いからです。
たとえば、
- 「こんな人を起用するなんて、企業の倫理観を疑う」
- 「もうこのブランドの商品は買わない」
といった声が数時間で拡散されれば、実際の売上や企業イメージに直接的なダメージを与えかねません。
そのため、企業の広報部や危機管理チームは常に「炎上シミュレーション」を行っており、タレントに問題が発覚した際には即座に対応フローを発動します。
今回の永野芽郁さんに関しても、「CM削除」という迅速な判断は、まさにこのリスクヘッジの一環だったと考えられます。
また最近では、タレント起用の段階でSNSスキャンや過去発言の精査、私生活の透明性までチェックするケースも増加中。つまり、スポンサーは“広告主”である以上に、リスクマネジメントのプロでもあるのです。
🔮今後の展望とユーザーが知っておくべきこと
🎯永野芽郁は活動継続できるのか?
現時点で、永野芽郁さんは所属事務所から契約解除や活動休止といった発表はされていません。CMは削除されたものの、契約は継続中という点もポイントです。つまり、“即引退”や“無期限活動休止”というような極端な処分は想定されていない状況だと見てよいでしょう。
とはいえ、タレントにとって「イメージ」は最大の資産。特に永野さんのような“好感度・透明感”を強みにしていた場合、今回の騒動はキャスティングやCM起用に大きな影響を与えることは避けられません。
ここから先、活動を継続できるかどうかのカギは、以下の2点にかかっています:
- ファン層の支持が維持されるか
→「信じて応援したい」という声が根強く残れば、復帰の後押しになります。 - 業界内の“様子見”期間をどう乗り越えるか
→数ヶ月から1年程度のメディア露出調整後に、映画・ドラマでの“静かな復帰”というシナリオが想定されます。
つまり、すぐに完全復帰とはいかずとも、時間をかけて少しずつ信頼を取り戻すルートは現実的に存在しています。ファンの声が、その後の方向性を左右すると言っても過言ではありません。
🎯信頼回復に必要な対応とは
芸能人がスキャンダルから信頼を取り戻すためには、単なる“時間経過”ではなく、戦略的かつ誠実な行動が求められます。永野芽郁さんのように清純派で支持されてきたタレントであればなおさら、回復の道のりは慎重に設計されなければなりません。
信頼回復において重要なのは、以下の3つのステップです。
1. 誠実な説明と謝罪のタイミング
報道直後の初動でうまく説明できなかった場合でも、時間を置いても構わないので、いずれは自身の言葉で誠実に語る場を設けることが不可欠です。ファンやスポンサーが最も望んでいるのは、「真実そのもの」よりも「真摯な姿勢」です。
2. “仕事”で信頼を取り戻す姿勢
テレビ出演や映画出演を無理に急がず、ナレーションや小規模な舞台、ラジオなど、露出をコントロールしながら地道に実績を積む方法も効果的です。特に「演技で評価される」ことは、イメージ回復に直結します。
3. 私生活の改善アピールやSNSでの透明性
炎上リスクを下げるために、私生活の安定や「変化」を見せることも重要です。必要以上の情報発信は避けつつも、ファンと適度につながるSNS運用は、“人柄”の再評価につながる可能性もあります。
結局のところ、信頼回復に一発逆転の方法はありません。しかし、小さな行動の積み重ねが“再評価”への道を開きます。永野芽郁さんにとっても、それは十分に可能な未来といえるでしょう。
🎯ファン・視聴者が取るべき冷静な視点とは
芸能人のスキャンダルに直面したとき、ファンや視聴者に求められるのは、「感情に流されすぎない冷静な視点」です。特に、SNSでの情報拡散が加速する中では、“一次情報”と“二次的な憶測”の区別がつきにくくなっています。
今回の永野芽郁さんのケースでも、
- 「事実なのか?」
- 「演出や編集によって印象操作されていないか?」
- 「報道のタイミングや狙いは?」
といった観点で情報を読み解くことが大切です。実際、週刊誌報道には芸能事務所同士の“パワーバランス”や、“世論操作”が背景にある場合もあります。
また、芸能人も人間であり、完全無欠な存在ではありません。
「誰しも過ちはある」「成長を見守る」という視点を持つことで、短絡的な“断罪文化”から距離を取ることができます。
そして、忘れてはならないのが、作品とプライベートを切り分ける視点です。演技や表現そのものの価値を評価する姿勢は、俳優にとっても社会にとっても健全な視聴態度といえるでしょう。
炎上が加速しやすい今だからこそ、視聴者側が持つ「冷静なまなざし」が、社会の空気を穏やかにする力にもなり得るのです。
🧾炎上の背景にあるメディア消費の仕組み
現代の炎上騒動は、単なる“失言”や“スキャンダル”だけで起きるものではありません。その背景には、私たちが情報をどう消費しているかというメディア構造の問題が横たわっています。
テレビ、ネットニュース、SNS、YouTube…。情報が氾濫するなかで、メディアは「クリックされること」「シェアされること」を最優先に記事を制作します。その結果、センセーショナルなタイトルや断片的な情報が拡散され、真偽よりも“話題性”が重視される状況が常態化しているのです。
特に芸能人の私生活は、“炎上ネタ”として扱いやすく、アクセス数を稼ぎやすいため、報道も過熱しがちです。これにユーザー側が過敏に反応し、拡散・批判を繰り返すことで、バズる→燃える→さらに報じられるという負のループが生まれます。
この構造の中で、私たち一人ひとりが**「何をシェアし、何を信じるか」**という判断力を持つことが、非常に重要になります。
つまり、永野芽郁さんのような芸能人の報道に接する際も、“炎上の構図”そのものを理解したうえで情報に向き合うことが、社会全体の空気を健全に保つ第一歩になるのです。
🧾批判と応援のバランスをどう取るか
芸能人にスキャンダルが起きたとき、多くの人が「批判するか」「応援するか」の二択で揺れ動きます。でも本来、この2つはどちらか一方だけではなく、両立できるものです。
たとえば、「不倫はよくない」と思う気持ちは自然ですし、行動に対して疑問を持つのも正当です。一方で、「これまでの努力や実績を一瞬で否定するのは違う」と感じるのもまた、まっとうな視点です。
重要なのは、感情的な極論に走らず、行動と人格を分けて考える姿勢です。
「今回の行動は残念だった。でも、才能や仕事ぶりは今でも評価している」
こんなスタンスこそが、健全な批判と応援のバランスを取る一つのヒントになるのではないでしょうか。
さらに、批判する側にも“責任”があることを忘れてはなりません。SNS上での言葉は、ときにタレント本人だけでなく、家族や共演者、企業関係者にも届きます。
「応援したいからこそ厳しく言う」ならば、その言葉に思いやりと冷静さを持つことが必要です。
応援するにも、距離を取るにも、“中立”という選択肢はいつでもあります。
一人ひとりがバランス感覚を持つことで、芸能人も、社会も、もう少し優しくなれるはずです。