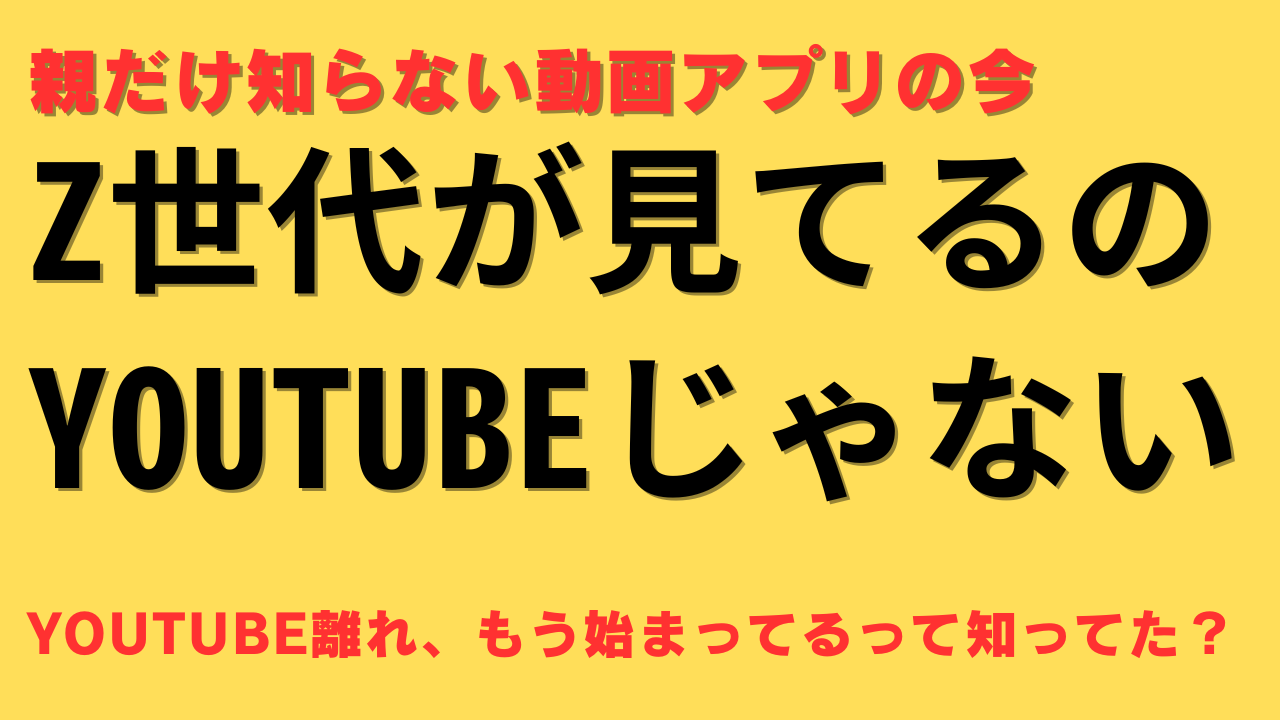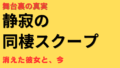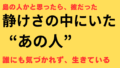「最近、うちの子YouTubeあんまり見てないな…」
そう感じたことはありませんか?
実は今、Z世代のあいだで「YouTube離れ」が密かに進んでいるんです。
長年、動画プラットフォームの王者として君臨してきたYouTubeですが、その座を脅かす新しいアプリたちが続々と登場。特にTikTokやBeReal.といった“リアル×短尺”を武器にしたSNSが、若者の心をわしづかみにしています。
「どうして若者はYouTubeを離れていくのか?」
「彼らが本当に求めているコンテンツとは何なのか?」
本記事では、Z世代の視聴行動の変化から、いま最も熱中されているアプリの実態まで、最新のデータとともに徹底解説していきます!
Z世代の「YouTube離れ」が加速している理由
Z世代の間でYouTube離れが進んでいるのは、動画の視聴スタイルや価値観そのものが変わってきたからです。かつては「じっくり見る動画」が主流だったのに対し、今の若者は「サクッと見て、すぐに次へ進む」テンポ感を重視しています。これは、TikTokなどのショート動画文化の影響が非常に大きいといえるでしょう。
さらに、Z世代は情報の“リアルさ”や“自分ごと感”を求めています。YouTubeでは演出や編集の凝った動画が多い一方で、リアルタイムな日常をそのまま共有するBeReal.のようなアプリに人気が集まっているのもその表れです。
また、YouTubeがショート動画(Shorts)に力を入れているものの、TikTokのようなパーソナライズ性や中毒性にはまだ追いつけていないのが実情。Z世代の「動画を見る目的」自体が、以前とまったく異なるものになってきているのです。
長尺コンテンツへの関心が薄れた背景
長尺コンテンツが敬遠される最大の理由は、「時間がもったいない」と感じるZ世代特有の感覚にあります。スマホネイティブ世代である彼らは、日常のすべてが高速で切り替わる環境に慣れており、動画も“長い説明”より“直感的に理解できる情報”を好む傾向が顕著です。
たとえば、10分以上の解説動画やVlogは「あとで見よう」と思いつつ結局見られないことが多い一方、TikTokやInstagramリールで流れてくる15〜60秒の動画は「今すぐ見られて、すぐ満足できる」手軽さがウケています。
この流れは、YouTubeに限らずNetflixやAmazon Prime Videoなどにも影響を与えはじめており、「ながら見」「倍速視聴」の増加も長尺離れのサインと言えるでしょう。もはやZ世代にとって、「時間をかけて見る価値があるかどうか」が最初に問われているのです。
リアルな体験を求める価値観の変化
Z世代が重視しているのは、「飾られていないリアルさ」。これはSNSの使い方にも表れており、映えた写真や編集された動画よりも、「今この瞬間の自分」をそのまま見せ合うスタイルが支持されています。
この傾向を象徴するのがBeReal.です。1日1回ランダムに届く通知で、2分以内に前後カメラで撮影し、加工なしの写真をシェアする──まさに“リアルを楽しむ”文化です。Z世代はこれを通じて「無理に盛らなくてもいい」「素のままでいい」という安心感を得ており、従来のSNSや動画配信サービスでは味わえない価値を感じているのです。
YouTubeのように編集や演出が強い動画は、「作られた世界」「距離を感じる」と捉えられることもあり、それが離れにつながっています。Z世代にとってSNSとは、“発信の場”であると同時に“つながる場”であり、リアルな感情や日常を共有し合うことこそが重要になってきているのです。
YouTube Shortsでは満たされないニーズ
YouTubeもZ世代の変化に対応するために「Shorts(ショーツ)」というショート動画機能を導入しました。しかし、Z世代が求める「スピード感」や「共感性」、「発見の楽しさ」においては、TikTokなどに比べてまだ物足りなさを感じているユーザーが多いのが実情です。
なぜなら、YouTubeは本来、長尺・高品質の動画を前提とした設計であり、アルゴリズムも“じっくり見る”前提で最適化されています。そのため、ShortsではTikTokのように次々と関連性の高い動画がスワイプで流れる感覚や、“今バズってるコンテンツ”の即時性に欠けてしまいます。
また、TikTokはZ世代にとって「自分が主役になれる場」でもあり、自己表現とコミュニティ参加の両方を満たしてくれます。一方、YouTube Shortsでは視聴者と投稿者の間にまだ“壁”があると感じている人も多く、気軽に参加するにはハードルが高いのです。
つまり、Z世代の「見る」だけでなく「関わりたい」「広がりたい」というニーズを、YouTube Shortsはまだ十分に汲み取れていないのです。
Z世代が熱中する新たなアプリとは?
YouTubeに代わってZ世代の関心を集めているのが、「TikTok」と「BeReal.」という2つのアプリです。どちらも共通しているのは、短時間で楽しめることと、“リアル”な体験や発信ができること。この2軸こそが、Z世代の心をつかむ鍵となっています。
TikTokはすでに世界的なブームとなっており、15〜60秒のショート動画をスワイプするだけで、次から次へと“自分好み”のコンテンツが流れてくる中毒性が特徴です。ユーザーは視聴だけでなく、気軽に投稿やリアクションができるため、自己表現の場としても活用されています。
一方で、BeReal.は派手さよりも「日常のリアルさ」を重視したSNSです。加工や演出を避け、友達との自然なつながりを楽しむスタイルは、他のSNSとは一線を画しています。特に“飾らない価値”を大切にする若者たちにとって、まさに理想のアプリといえるでしょう。
このように、Z世代は「時間を奪われず、かつ自分を素直に表現できる」プラットフォームを自然と選ぶようになっており、従来型のYouTubeとは異なる新たな“動画の楽しみ方”が広がっているのです。
TikTokが圧倒的な人気を誇る理由
TikTokがZ世代から圧倒的に支持される理由は、なんといっても「時間をかけずに楽しめる上に、自分も簡単に発信できる」からです。15〜60秒の短尺動画が中心のTikTokは、通学中やスキマ時間でも気軽に楽しめるコンテンツが並び、まさに“ながら視聴”に最適化されています。
さらに、TikTokの最大の強みは、驚異的なアルゴリズム精度にあります。ユーザーが見た動画やリアクションをもとに、「あなたが気に入りそうな動画」を次々と表示。興味のあるジャンルの動画が際限なく流れてくるため、つい何十分も見続けてしまう「沼」状態にハマる人が続出しているのです。
加えて、投稿のハードルが低いのもZ世代に刺さるポイント。難しい編集スキルがなくても、テンプレートや音源を使えば、誰でも“それっぽい”動画をつくれてしまいます。つまりTikTokは、見る側も発信する側も主役になれるアプリとして、Z世代のライフスタイルに深く浸透しているのです。
短尺×中毒性の高いUIで滞在時間が伸びる
TikTokの中毒性を支えているのが、短尺動画と“スワイプで次へ”という直感的なUI(ユーザーインターフェース)です。1本の動画がわずか15〜60秒で完結するため、「あと1本だけ…」が「気づけば30分見てた!」という状態を生みやすい構造になっています。
この「短さ」は単に手軽さだけでなく、ユーザーの集中力を切らさず、常に刺激を与え続ける設計にもつながっています。TikTok側のアルゴリズムが、視聴履歴や“止まった秒数”などの細かい動きを分析し、「次に見たい」と思う動画を次々と提案してくれるため、ユーザーは受け身のまま楽しみ続けることができるのです。
YouTubeやInstagramと異なり、ホーム画面=おすすめ動画再生の“即開始”仕様も、滞在時間を増やす要因のひとつ。TikTokは動画の中身だけでなく、UX(ユーザー体験)全体で「やめ時を見失わせる設計」が徹底されているため、Z世代の滞在時間が他SNSと比較して圧倒的に長いのです。
エンタメ性とアルゴリズムの最適化が強み
TikTokがZ世代を夢中にさせるもう一つの理由は、エンタメ性の高さと、それを最大限に引き出すアルゴリズムの存在です。TikTok上のコンテンツは、音楽・ダンス・おもしろネタ・ライフハック・あるある系などジャンルが多彩で、どれも「見てすぐ楽しめる」軽快なテンポ感が魅力です。
しかも、TikTokのアルゴリズムは他のSNSと比べて“興味ベース”の推薦制度が非常に精巧。フォローしていないアカウントの動画でも、自分の関心とマッチすればどんどん表示されます。その結果、ユーザーは「なんとなく開いたのに、気づけば見入ってしまう」体験を繰り返しやすくなっているのです。
さらに、音楽との連動性が高いのも特徴で、「この音楽が流れたらこのネタ」という“文化のテンプレ化”が自然に生まれやすく、コンテンツ制作の敷居を下げながら、視聴の没入感も高めています。Z世代にとってTikTokは、ただのSNSではなく、「発見」と「表現」が毎日更新されるエンタメ空間なのです。
BeReal.が注目される“リアルさ”の価値
Z世代がBeReal.に惹かれるのは、「リアルな自分を、そのまま共有できるから」。SNSにありがちな“盛り文化”や“見栄の張り合い”に疲れた若者たちにとって、BeReal.の「加工しない、作らない」というルールはまさに救いとも言える存在です。
このアプリは、毎日1回、ランダムな時間に通知が届き、2分以内にその場の様子を前後カメラで撮影して投稿するという非常にユニークな設計。誰もが同じタイミングで投稿することで、「今この瞬間」をみんなで共有する感覚が生まれ、友達とのつながりがより“リアル”に感じられるのです。
Z世代は、「共感」や「素直な感情のやりとり」を何よりも大切にしています。そのため、映えやフォロワー数に縛られず、ただ日常を切り取るだけのBeReal.は、新しい時代のSNSとして受け入れられているのです。
見せびらかすSNSから、つながりを感じるSNSへ──その象徴がBeReal.だといえるでしょう。
1日1回の通知で「今」を共有する設計
BeReal.の最大の特徴は、毎日1回ランダムな時間に届く通知と、その通知から2分以内に投稿しなければならないという“制限付きのリアルタイム性”です。この設計が、他のSNSにはない独自の体験を生み出しています。
通知が来た瞬間、ユーザーは前後カメラで同時に撮影。つまり「自分が今どこで、何をしていて、どんな顔なのか」を隠さずに共有することになります。作り込む時間も、フィルターをかける余裕もありません。だからこそ、投稿された内容は飾り気のない「そのままの自分」なのです。
この“今を切り取る”スタイルは、Z世代にとって新鮮で心地よいもの。「他人と比べなくていい」「取り繕わなくていい」という安心感が、BeReal.の人気を支えています。従来のSNSのように“映えを競う”のではなく、「友達の日常を垣間見る」こと自体が楽しい──そんな価値観の変化が、この設計によって見事に実現されているのです。
Z世代が加工や演出を嫌う理由とは?
Z世代がSNSで「加工された世界」に違和感を抱くのは、幼いころからSNSに触れて育ってきたからこそ、その“裏側”をよく知っているからです。盛られた写真、編集された完璧な日常、フィルターで整えられた顔──そうした“作られた美”に慣れすぎた彼らにとって、それはもはやリアリティを感じない存在になりつつあります。
むしろ今、彼らが求めているのは「等身大の自分を肯定してくれる場」。BeReal.のように、誰もが一斉に、飾らず、同じルールで投稿する仕組みは、比較や競争ではなく“共感”を生む設計です。「あ、みんなもこんな感じなんだ」と安心できることが、Z世代にとっては大切なのです。
さらに、SNS疲れや自己肯定感の低下が社会課題としても注目される中で、Z世代は“気を使わずにいられる場所”を本能的に求めています。加工や演出が不要なプラットフォームは、そんな彼らにとっての「逃げ場」でもあり、リアルなつながりを取り戻す手段にもなっているのです。
YouTube離れから見えるSNS戦略の転換点
Z世代のYouTube離れは、単なる流行の変化ではなく、デジタルコミュニケーション全体の価値観がシフトしている証拠です。かつては「多くの人に届く」ことが重視されていたSNS戦略も、今は「深く共感される」ことが何より重要になってきています。
YouTubeを中心としたコンテンツ戦略では、視聴数や再生時間といった“量的指標”が成功の鍵でした。しかし、Z世代はその「数字」を鵜呑みにせず、本当に自分に刺さる内容かどうかで評価する傾向が強いのです。その結果、リアルな感情や日常をベースにしたTikTokやBeReal.のようなプラットフォームが存在感を増しています。
つまり、これからのSNS活用においては「質の高い情報発信」だけでなく、「ユーザーとの距離感」や「共感の設計」が勝負の分かれ目になるということ。企業も個人も、Z世代に届く“等身大のコンテンツ”とは何かを見直す時期に差しかかっているのです。
今後の動画プラットフォームの潮流とは
これからの動画プラットフォームは、「ただ見る」だけでなく、“参加する”“共感する”という体験軸がより一層重要になっていきます。Z世代の行動から読み取れるのは、「情報の発信元」よりも「自分との距離感」や「リアルなつながり」が重視されるという明確なトレンドです。
その流れを象徴するのが、コメントやリアクション機能が豊富なTikTokや、毎日の生活を“そのまま”共有するBeReal.のような設計です。どちらも、視聴者を受け身にさせず、アクションを促す仕組みを取り入れることで、より深いエンゲージメントを生んでいます。
また、今後注目されるのは「ライブ機能」や「共同編集コンテンツ」など、双方向性のあるメディア体験です。すでにInstagramやYouTubeもライブ配信やショート動画に力を入れていますが、ただ模倣するだけではZ世代の関心を引き続けることは難しいでしょう。
求められるのは、“ユーザーが主役になれる”体験。そのためには、動画の長さや質以上に、どれだけ共感し、参加できるかを設計することが、今後の動画プラットフォームにとっての成功条件となっていくはずです。
マーケターや企業が取るべき対応策
Z世代のYouTube離れが進む今、マーケターや企業に求められるのは、「どのプラットフォームに広告を出すか」よりも、「どんなコンテンツ体験を提供するか」という視点への転換です。つまり、“場所”より“中身と共感性”が問われる時代に入ったということです。
まず重要なのは、Z世代の価値観にフィットしたメッセージ設計です。彼らは、過度な演出や押しつけがましい広告を嫌い、「共感できるリアルな声」「素のままの情報」に心を開きます。そのため、いわゆる“広告っぽくない広告”──たとえばTikTokでのユーザー参加型キャンペーンや、BeReal.風の素朴なコンテンツ──が効果的です。
また、投稿内容に“ユーザーの視点”を取り入れることも鍵になります。企業が一方的に発信するのではなく、「共感」や「共創」を軸にしたコンテンツ設計が、Z世代の信頼を得る近道です。
従来の大量露出型マーケティングから、「信頼ベースの関係性づくり」へ。これが、Z世代と本気で向き合うための、新しいコミュニケーション戦略の出発点なのです。
TikTokやBeRealを活かした施策事例
Z世代向けに成果を上げている企業は、TikTokやBeRealの特性をうまく活かしたプロモーションを展開しています。その共通点は、「企業が主役にならない」こと。あくまでユーザー視点を尊重し、リアルな共感や体験を軸にした施策が支持されています。
たとえばTikTokでは、コスメブランドが「#すっぴんから3分で変身」などのハッシュタグチャレンジを開催し、ユーザーが自分で動画を投稿・参加するスタイルが話題になりました。企業側は目立ちすぎず、あくまで“場を提供する”形で、自然なバズを生んでいます。
一方BeRealにおいては、飲料メーカーが「今日の1杯」と題して、社員の日常の中で商品を使っている様子をそのまま投稿。演出なし・加工なしのリアルな姿が「親近感が湧く」「無理がなくて好印象」とSNSで広まりました。
これらの施策に共通するのは、“企業の魅力”を見せるのではなく、“人としてのリアル”を伝えるというアプローチ。Z世代に響くのは、派手な演出よりも、日常に溶け込んだ信頼感なのです。
Z世代とつながるには「リアル」と「共感」がカギ
Z世代と深くつながるには、「リアルな感情」と「共感できる体験」が必要不可欠です。彼らは、きれいに整えられた情報や、押し売り感のある広告にはすぐに敏感に反応し、“心がこもっていない”と感じると一気に離れてしまいます。
だからこそ、企業や発信者に求められるのは、“本気で向き合っている姿勢”を見せること。それは見た目を整えることではなく、たとえば「社内のリアルな裏側を見せる」「実際に働く人の声をそのまま届ける」「ユーザーの意見をコンテンツに反映する」など、“嘘のない姿勢”にこそ共感が集まるのです。
また、Z世代は「共に考え、共に動くこと」に価値を感じる世代です。自分も参加できる、意見を届けられる、という仕組みがあれば、自然とブランドへの愛着や信頼感が育まれます。
つまり、Z世代とつながるには、「飾らない情報」「気取らない発信」「共に作る姿勢」の3つがカギ。これからのSNS戦略は、“共感されるリアル”をどうデザインするかにかかっていると言えるでしょう。