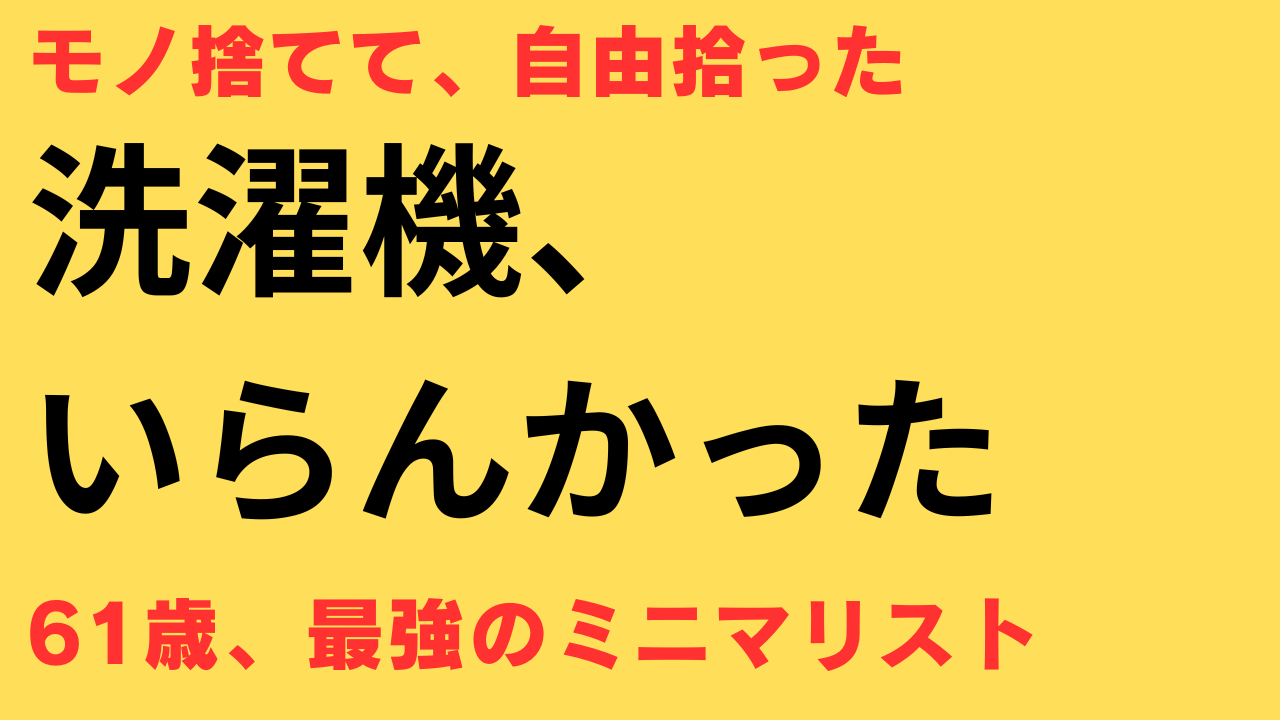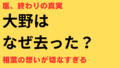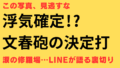「えっ、洗濯機も捨てたの!?」
そんな驚きの声がスタジオに響いたのは、タレントの磯野貴理子さん(61)が“洗濯機なし生活”を4ヶ月も続けていると明かしたときのこと。終活の一環として始めたこの生活に、多くの人が関心を寄せています。
とはいえ、誰もが「本当にそんな生活できるの?」と不安に思うはず。便利な家電を手放してまで、なぜ貴理子さんは“ミニマル”な道を選んだのでしょうか?
年齢を重ねるにつれ、「身軽に、快適に、自分らしく生きたい」と願う人は増えています。でも実際に何から始めればいいのか、ちょっと迷ってしまいますよね。
この記事では、貴理子さんの事例を通して「洗濯機なし生活」のリアルと、60代から始める終活的ミニマリズムのヒントをわかりやすく解説していきます。きっとあなたの生活にも、新しい気づきがあるはずです!
終活で“洗濯機なし生活”を始めた磯野貴理子の決断
乾燥機付き洗濯機の故障がきっかけだった
「洗濯機が壊れたのが始まりなんです」
磯野貴理子さんが“洗濯機なし生活”を始めたきっかけは、乾燥機能付き洗濯機の突然の故障でした。買い替えるか迷ったものの、とっさに手洗いをしてみたところ、「あれ、意外となんとかなるかも」と感じたのだとか。
たらいに水を張って、洗剤を溶かし、手でゴシゴシ。昔ながらの洗濯方法は、最初こそ大変だったものの、やってみると「意外とシンプルで悪くない」と思えたそうです。
ここで「買い直す」選択をしなかったのが、終活の視点。年齢的にも、物を減らしていくタイミングと重なり、「このまま洗濯機なしでいこう」と決断。便利さを手放してみたことで、新しい暮らしの選択肢に気づいた瞬間でした。
たらいで手洗いする生活に変えて気づいたこと
手洗いの洗濯生活を始めて、磯野貴理子さんがまず驚いたのは「洗濯って、案外“自分のペース”でできるんだな」ということ。洗濯機があると、ついつい“溜まってから一気に洗う”というスタイルになりがちですが、手洗いだと自然と“毎日ちょこちょこ洗う”流れになるそうです。
この小さな変化が、生活全体にも良いリズムをもたらしました。洗濯物をじっくり見て、自分の手で清潔にしていく時間には、ちょっとした達成感と、心地よさがあるといいます。
また、「洗濯物の量が減った」「服を大切に着るようになった」といった気づきも。洗濯機に頼らない生活は、ただの“我慢”ではなく、自分にとって本当に必要なものを見極める力をくれたようです。
新しい洗濯機は「買わない」と決めた理由
「買い替える必要、ないよね?」
磯野貴理子さんがそう感じたのは、手洗い生活を続けてみたことで「洗濯機がなくても困らない」と実感したからでした。最初は応急処置のつもりだった手洗いが、気づけば4カ月も続いていたのです。
もちろん、洗濯機があると便利なことも多いです。でも、「家電がある=豊かさ」という価値観から一歩引いてみると、「本当にそれは今の自分に必要?」という問いが生まれます。貴理子さんの場合、それが“終活”というライフステージとリンクしていたのです。
洗濯機を買い直せば、設置の手間、電気代、水道代、そしてスペースも必要。でもそれがなくても、生活はちゃんと回っている。「じゃあ、なくていいよね?」という選択は、物に振り回されない“身軽な暮らし”への第一歩だったのでしょう。
ソファも冷蔵庫も手放す?終活の本気度
洗濯機に続いて、なんとソファまで手放したという磯野貴理子さん。その理由はとてもシンプルでした。「くつろぎすぎちゃうから」。リビングの主役ともいえるソファをあえて処分し、代わりに選んだのは“ベンチ”。この行動からも、貴理子さんの“本気の終活”ぶりが伝わってきます。
さらに彼女は、今後「冷蔵庫も手放そうかと考えている」と発言し、スタジオ中をあ然とさせました。冷蔵庫がない生活なんて想像しづらいかもしれませんが、実際に“毎日買い物に行けばそれで済む”というシンプルな発想も可能です。
物が多いと、家も心も管理が大変になります。だからこそ貴理子さんは、ひとつずつ手放して「本当に必要なものだけ」に絞り、自分のペースで心地よく暮らす方法を模索しているのです。
ミニマリスト的発想で「くつろぎすぎ」を断捨離
「ソファがあると、ついゴロンとしちゃって動かなくなるんです」
そう話す磯野貴理子さんが選んだのは、“くつろぎすぎ”を手放すという選択。快適さを追求するあまり、身体も気持ちもどんどん「だらけていく」ことに気づいたのだそうです。
そこでソファを処分し、代わりに導入したのが「背もたれのないベンチ」。座ると自然と姿勢が正され、テレビを見ながらダラダラする時間も減っていったそうです。結果として、部屋も気持ちもシャキッと整うようになったと語っています。
この発想は、まさに“ミニマリスト思考”そのもの。物を増やすより、減らすことで得られる自由とコントロール感。必要以上に「楽」ではなく、適度な緊張感こそが、自分らしい暮らしを支えてくれるという考え方です。
冷蔵庫を手放す“その先の生活”とは
「冷蔵庫も、なくても何とかなるかもしれない」
磯野貴理子さんがそう感じ始めたのは、洗濯機やソファを手放しても困らなかった実体験があったからこそ。実際、冷蔵庫を使わずに生活する人は少数ながらも存在しており、日々の買い物と食事のスタイルを変えれば可能だとされています。
たとえば、1日分の食材をその都度買い、すぐ調理して食べきる。これなら食材の無駄も減り、冷蔵庫の電気代やスペースも不要になります。毎日の買い物が“ちょっとした運動”にもなり、健康維持にもつながるかもしれません。
もちろん、暑い季節や保存食の管理など課題もありますが、「それを工夫するのも生活の一部」と考えるのが貴理子さん流。便利なものに囲まれすぎない暮らしは、「自分で考え、動き、選ぶ」自由を取り戻す行為でもあるのです。
洗濯機なし生活って現実的?メリットと課題を比較
洗濯機がないからこそ得られる自由と心地よさ
「ない方が、かえって楽だったんです」
洗濯機なし生活を経験した人の多くが語るのは、“意外な快適さ”です。磯野貴理子さんもその一人。手洗いの洗濯はたしかに手間がかかりますが、そのぶん「洗濯物に向き合う時間」が生まれ、暮らしにリズムと丁寧さが戻ったといいます。
洗濯機の音や設置場所、掃除の手間など、意外と「持っていること自体のストレス」に気づく人も少なくありません。さらに、手洗いすることで服の消耗も少なくなり、自然と“モノを大切にする気持ち”が育まれるという声も。
そして何より、「洗濯機がなくても生活できる」という自信が、自立心や自由を後押ししてくれるのです。少ない物で暮らすことで、選択肢が減るどころか“暮らし方の幅”が広がっていく感覚。これは実際に体験しないと分からない醍醐味です。
「干す・絞る・たたむ」が意外と楽しい?
「まさか自分が“洗濯を楽しむ”日が来るなんて」
磯野貴理子さんもそう語るように、洗濯機を使わない生活では、干す・絞る・たたむという工程が主役になります。一見手間に思えるこの作業が、やってみると案外楽しいという声も少なくありません。
特に、干す作業は“自然との対話”のような感覚。日差しや風の具合を見ながら「今日はこの場所に干そう」と考える時間は、忙しない日常の中で心が整うひとときです。
また、手で絞ることで布の質感を再認識したり、たたむときに「この服、好きだな」と感じたり。ひとつひとつの作業が“自分の暮らしを整える儀式”に変わっていきます。
洗濯機に任せていた作業を自分の手に取り戻すことで、生活全体にも“丁寧さ”が広がる。それが、この生活スタイルが注目される理由のひとつです。
水道代や電気代の節約効果にも注目
洗濯機を使わない暮らしは、意外と家計にもやさしいんです。
電気代・水道代の両方において、洗濯機は“見えにくい出費”を生む家電の代表格。毎日ではないにしろ、何度も稼働すれば、それだけ電力と水を使います。
磯野貴理子さんのように、たらいでの手洗いに切り替えると、まず電気代はほぼゼロに。そして手洗いは必要最低限の水だけを使うため、水道代も自然と抑えられます。
また、「洗濯するための洗剤や柔軟剤の量が減った」「服の消耗が少なくなったことで買い替え頻度が減った」といった“周辺コスト”の削減も見逃せません。
生活費を削るというより、「暮らしを見直すことで、結果的に無駄が減る」というのがこのスタイルの特徴。節約は“我慢”ではなく、“選び直す”ことから始まる——そう感じさせてくれる暮らし方です。
不便さもある?手洗い生活のリアルな声
もちろん、すべてが“快適”というわけではありません。
洗濯機なし生活には、実際にやってみて初めてわかる不便さもあります。たとえば、服を1枚ずつ手洗いする作業は、疲れている日には少しハードルが高く感じられます。
また、手が荒れやすい人にとっては、洗剤の成分や水温にも気を配る必要があります。特に冬場の冷たい水での洗濯は、想像以上にツラいもの。こうした現実的なデメリットも、手洗い生活の“リアルな一面”です。
それでも、磯野貴理子さんのように「手間があるからこそ暮らしに向き合える」と感じる人も増えています。不便だからこそ、自分なりの工夫が生まれ、結果的に“暮らしをデザインする感覚”が育つという声も。
洗濯機を手放す選択は、快適さと不便さのバランスを見直すきっかけ。だからこそ、その生活に価値を感じる人が少しずつ増えているのかもしれません。
大物洗いや冬場はどうする?
「手洗い生活って、毛布やシーツはどうしてるの?」
こうした疑問は当然浮かびます。実際、バスタオルや寝具などの“大物洗い”は、手洗い生活における大きな課題のひとつです。磯野貴理子さんも、この点については“無理をしない”というスタンスをとっています。
たとえば、毛布や厚手の衣類などは、コインランドリーを利用したり、季節ごとに専門のクリーニング店に任せるなど、手洗いと外部サービスをうまく併用して対応しているケースが多いようです。
また、冬場の冷たい水での手洗いには、ゴム手袋の活用や、お湯を少し混ぜるなどの工夫も効果的。洗濯の頻度を少し減らして、着回しや重ね着で対応するというライフハックもあります。
すべてを一人で完璧にこなすのではなく、「できるところは自分で」「無理な部分は外注」という柔軟な姿勢が、長く続けるコツ。それが“洗濯機なし生活”を現実的にする秘訣かもしれません。
途中で挫折しないための工夫とは
洗濯機なし生活にチャレンジしたものの、「結局、続かなかった…」という声もあります。やはり日々の手洗いは、慣れるまでに根気が必要。しかし、ちょっとした工夫で“挫折せずに続けられる環境”はつくれます。
まず大切なのは、“洗濯物を溜めすぎないこと”。毎日少量ずつ洗えば、手洗いでもそれほど負担は感じません。特に下着やタオルなどは、ルーティンにしてしまうと意外とあっという間に終わります。
次に、道具を活用すること。たとえば、手を痛めないように柔らかいゴム手袋を用意したり、脱水代わりに足で踏む「踏み洗い」を取り入れたりすると、作業がぐっとラクになります。
さらに、“やらなきゃ”ではなく“自分の時間”と捉えるマインドの切り替えもポイント。洗濯の時間を、自分と向き合う“暮らしの瞑想”として取り入れることで、義務感よりも充実感が勝ってくるはずです。
60代から始める終活×ミニマリスト生活のすすめ
モノを減らすことで見えてくる“自分らしい暮らし”
「これは必要?それとも、なくても平気?」
60代という節目は、人生を見つめ直し“これからの暮らし”を考える絶好のタイミング。磯野貴理子さんのように、終活としてモノを減らし始める人が増えています。
物を手放すという行為は、単なる“片付け”ではなく、自分の価値観や生活スタイルと向き合う行為でもあります。洗濯機やソファといった“当たり前にあるもの”を見直してみると、そこには驚くほどの自由と選択肢が広がっています。
実際、「なくても困らなかった」「むしろ気持ちが軽くなった」という声は少なくありません。モノに囲まれすぎない生活は、自分にとって本当に大切なことや、心から必要としているものを見つけやすくしてくれます。
“60代からのミニマルな暮らし”は、無理せず、自然体で始められる新しい終活のカタチなのです。
「なくても困らない」モノに気づく体験
「これ、最近使ってないかも…」
そんなひと言から始まるのが、終活×ミニマリスト生活の第一歩です。洗濯機やソファのような“生活の中心”に思えるモノでも、実際に手放してみると「なくても困らない」ことに気づくケースは意外と多いんです。
貴理子さんのように、故障をきっかけに買い替えをやめてみる。あるいは、掃除のたびに動かすのが面倒で処分を決意する。きっかけは小さなストレスでも、それを放置せず向き合うことで、「自分に本当に必要なもの」が見えてきます。
しかも、この気づきは“暮らし”だけでなく“心”にも影響を与えます。モノが減ることで選択肢がクリアになり、決断のスピードや気持ちの余裕にもつながるのです。
大切なのは、「手放すこと=不便」ではなく、「自分らしく整えること=快適」だという意識。この考え方が、今60代から注目されている理由です。
「本当に必要なもの」だけに囲まれる安心感
モノが少ないと、逆に不安になるんじゃない?
そんな声があるのも事実ですが、実際には「必要なものだけがある暮らし」は、驚くほど安心感に満ちています。選び抜いたモノだけに囲まれているということは、つまり“自分でコントロールできる範囲に暮らしを収めている”ということ。
洗濯機がなくても、自分の力で毎日を回せる。ソファがなくても、姿勢よく過ごせる。冷蔵庫を使わずに、毎日きちんと食べられる。そうした日々の積み重ねは、「私はちゃんとやれている」という小さな自信にもつながります。
この“安心感”こそが、終活やミニマリズムの真の魅力。老後に向けて不安を抱えている方こそ、自分の生活を自分で作っていける実感を得られるのです。
自分にとっての「ちょうどいい暮らし」を見つける。それは派手じゃなくても、穏やかで満たされた生き方への第一歩かもしれません。
洗濯機なし以外にも手放せる家電・モノとは?
洗濯機を手放しても困らなかったなら、ほかにも減らせるモノがあるかもしれません。実はミニマリストの中には、テレビや電子レンジ、炊飯器、さらにはカーペットや食器棚など、さまざまな“当たり前アイテム”を見直している人がいます。
貴理子さんのように、「冷蔵庫もいらないかも」と考えるのは一見極端に思えるかもしれませんが、その背景には“自分の生活パターンを見直す”という視点があります。
たとえば、
- 外食や買い物の頻度が多ければ冷蔵庫は不要かも?
- 電子レンジよりフライパンや鍋で十分かも?
- テレビはスマホやタブレットで代用できるかも?
こうして「自分の暮らしに本当にフィットしているのはどれか?」と考えることで、家電や家具に縛られない自由な生活が手に入ります。
“持つことが当たり前”になっていた家電やモノたち。実はそのいくつかは、手放すことで生活がもっとシンプルに、快適になる可能性を秘めているんです。
「一人暮らし×終活」で整える生活の土台
一人暮らしと終活。この2つが重なると、暮らし方を“整える”重要性がぐっと高まります。特に60代以降は、健康や体力、万一の備えまで見据えて、「いかに無理なく暮らせるか」が大切なテーマになりますよね。
モノが多いと、掃除が大変。管理も手間。そしていざというとき、家族や第三者が対応しづらくなるという側面もあります。だからこそ、一人暮らしの終活は「生活をシンプルにする」ことが最大の安心材料になるのです。
洗濯機を手放す、冷蔵庫を見直す、家具を減らす…。こうした選択は、単なる節約ではなく、自分の生活を“自分で設計する力”を育てるもの。
結果として、災害や入院など“想定外の出来事”にも慌てず対応できるし、気持ちにゆとりが持てるようになります。
「自分にとってのちょうどいい暮らし」が、一人暮らしの終活を支える強い土台になるんです。
まとめ|“洗濯機なし”は終活の新しい選択肢になる
貴理子さんのように、自分に合った暮らし方を見つけよう
洗濯機を捨てる——そんな大胆な行動が、終活の一歩になるなんて、少し前までは考えもしなかったかもしれません。でも、磯野貴理子さんの姿を見て、「自分に本当に合った暮らし方って何だろう?」と立ち止まるきっかけになった方も多いのではないでしょうか。
大切なのは、“便利”や“常識”にとらわれず、今の自分にとっての快適さ・心地よさを基準に選び直すこと。そして、それは決して“我慢”ではなく、“自由”を取り戻す作業でもあります。
終活=寂しいこと、と捉えられがちですが、実は“自分らしく生きる準備”のこと。洗濯機なし生活もそのひとつの手段として、もっと前向きにとらえてみてもいいのかもしれません。
今あるモノを見直して、身軽になったその先に、自分らしい人生が待っている。そう思えるヒントが、このテーマには詰まっています。